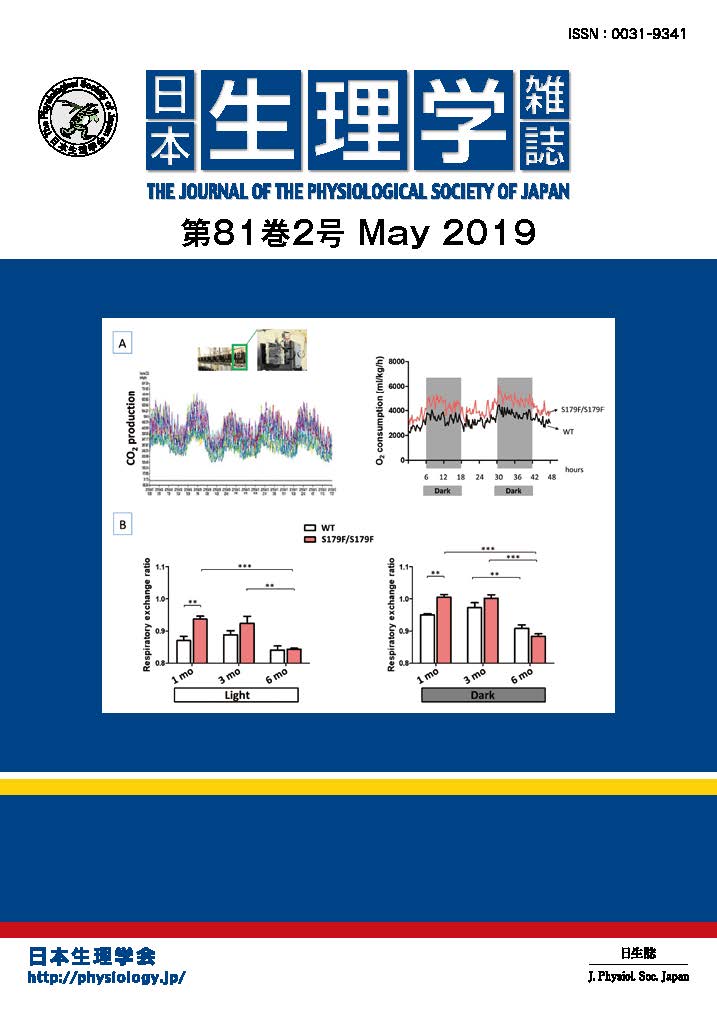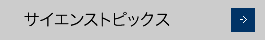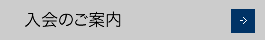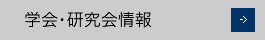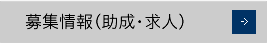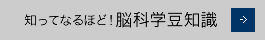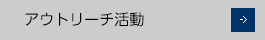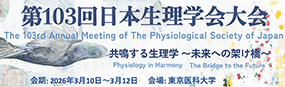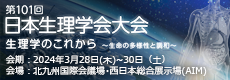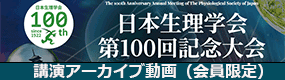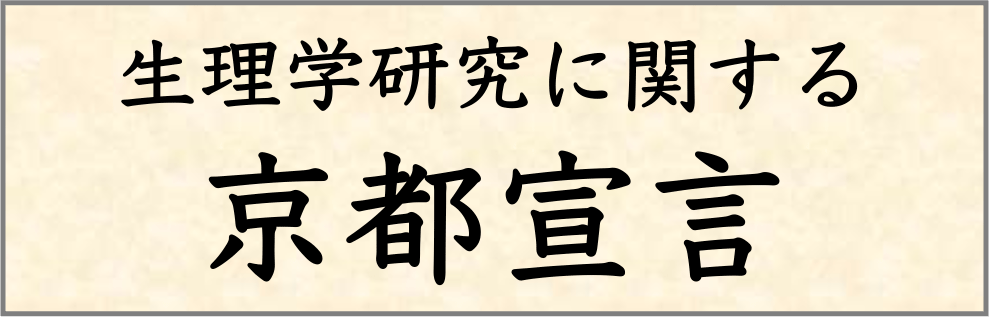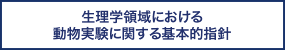2024年3月29日の総会において日本生理学会の理事長を拝命しました生理学研究所の久保義弘です。これまでは、栗原敏理事長、丸中良典理事長、石川義弘理事長の下で、国際交流・集会担当の副理事長を務めてきました。今後4年間、歴代の理事長をはじめとする方々の築かれた100年を越える良き伝統を守りつつ、時代の流れに応じた新しい取り組みを行い、生理学と生理学会のさらなる発展に向け尽力したいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。
理事長就任にあたり、熟慮を重ねて、副理事長を選出させていただきました。まず、前期から引き続き、「庶務・事務局長」担当を平野勝也先生に、「学術・研究」担当を赤羽悟美先生にご依頼しました。さらに、新たに、「財務・ダイバーシティ」担当を西谷友重先生に、「編集・情報発信」担当を花田礼子先生に、「教育・キャリア形成」担当を小野富三人先生に、「国際交流・将来計画」担当を樽野陽幸先生にお願いしました。幸いなことに全員がご快諾下さり、私が思い描いていた通りのチームを構築することができました。副理事長の方々と緊密に意思疎通を図り、そして、理事・監事・各種委員会委員長・学会事務局の、皆様のご協力をいただき、運営活動を行っていきたいと思います。
生理学は機能生命科学・医科学の根底にあり、包含する分野は原義的に極めて広く、その重要性は時代を超えて続くものだと思います。ただ、日本生理学会では、評議員の高齢化および会員数の減少による先細りが懸念される分岐点にあります。そのため、多様な新会員の入会と定着を促進するために、求心力を強化することが課題となっています。
以下に、生理学会の果たすべき役割と、今後の課題、私が考える方向性等について記します。
(1) 優れた研究成果の発表・享受の場: 大会等において、世界を先導する魅力的な研究成果の講演等が行われること、個々人の興味に基づき徹底的になされた研究の成果や、新しい学際的アプローチにより達成できた成果等が発表されること、建設的で有益な討論ができることは、学会の生命線だと思います。
(2) 様々な分野の包含: 今後の生理学の在り方として、広義の生理学に関連する様々な分野の方々が生理学会をホームグラウンドと感じて、参加いただけることは重要です。また、求心力を高め、様々な分野を包含していくことは、今後の会員や評議員の減少の懸念を踏まえると喫緊の課題だと思います。
(3) 次世代育成への貢献: 教育に関する諸活動も、学会の果たすべき重要な役割です。学部等における生理学教育の充実、次世代の研究者の育成に加え、多様なキャリアパスの育成等にも貢献したいと思います。
(4) ダイバーシティの推進: ダイバーシティの推進は自然な流れであり、また、社会や学会を強く、豊かにするものです。委員会活動や大会のプログラムの構築等においてその推進を目指し、必要な各種サポートを強化したいと思います。
(5) 国際化の推進: 国際化の推進も自然な流れです。これまで以上に、各国の生理学会やIUPS、FAOPS等との連携を進め、日本の生理学のプレゼンスを高めるとともに、国際的に開かれた学会を目指します。また、世界をリードする大きな生理学会のひとつとして、生理学のグローバルな振興への貢献も検討したいと思います。
(6) 地方会の活発化: 生理学会の大きな特徴のひとつとして、地方会が充実していることがあります。大学院生を含む若手研究者等の初めての口頭発表の場等として、今後、さらに活発化していただきたいと思っています。また、これまで同様、日本の各地で大会が開催される伝統を大切にしたいと思います。
(7) 予算の有効活用: 一昔前、生理学会の財務状況は危機的でしたが、現在は、ある程度の正味財産を有しています。将来に備えて大切に確保するだけでなく、種々の活動に有効活用し学会の活性化につなげることが重要だと思います。それにより、求心力を高め、会員数の増加を図り、今後の財務状況のさらなる安定化につなげたいと考えています。
(8) 会員のベネフィットの充実: 生理学会は、ほぼ、会員の会費で運営されており、会員が、会員であることの恩恵を感じられることは重要です。充実した大会に参加し、成果発表と研究・教育等に関する情報収集ができること、日生誌の受領、生理学エデュケーターの資格の取得等がありますが、様々なニーズを持つ会員それぞれが、会員であることの恩恵を実感できるように、提供できることを考えたいと思います。
(9) アウトリーチ活動: 他方、学会は会員のみのために存在するわけではありません。社会に対し貢献すること、すなわち、生理学に関する市民向けの情報発信、小中高生等に対するアウトリーチ活動、学術に関するオピニオンの表明等は、学会の果たすべき重要な役割だと思います。
(10) 新しい情報発信: 情報発信の方法は、年々変化を遂げています。これまでの、印刷体、ホームページ、およびメールによる発信を安定的に行うと共に、特に社会との連携において、各種SNSを用いた情報発信についても注意深く検討したいと思います。
以上の通り、広義の生理学の、高く、幅広い学術研究、および教育の推進に貢献することを根幹に置き、「全部入り」の求心力の高い学会を目指して諸活動を行いたいと思います。成し遂げることは簡単ではありませんが、知恵を出し合って、全体としての最適解を模索しつつ進みたいと思います。
私自身が生理学会大会で初めて発表を行った時の緊張感やワクワク感は、今も鮮明に記憶しています。その思い出は季節感とリンクしていて、春の訪れが近くなると思い起こします。生理学という学問に対する興味を共有する多数の方々が集まり、真摯に発表、議論、情報交換を行う「学会」の熱さに魅せられました。大会において、参加者がそれぞれに有益な情報を得て、充実した人的交流を行い、大会に参加して有意義だった、楽しかったと思えること、また、会員が学会に入会してよかったと思えることを、原初的に大切なことだと思い、大切にしていきたいと思います。
今後の日本生理学会と生理学の発展は、会員の皆様のご協力なしでは成し遂げられません。ご支援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
2024年4月2日
久保 義弘
日本生理学会 理事長
自然科学研究機構生理学研究所 神経機能素子研究部門 教授