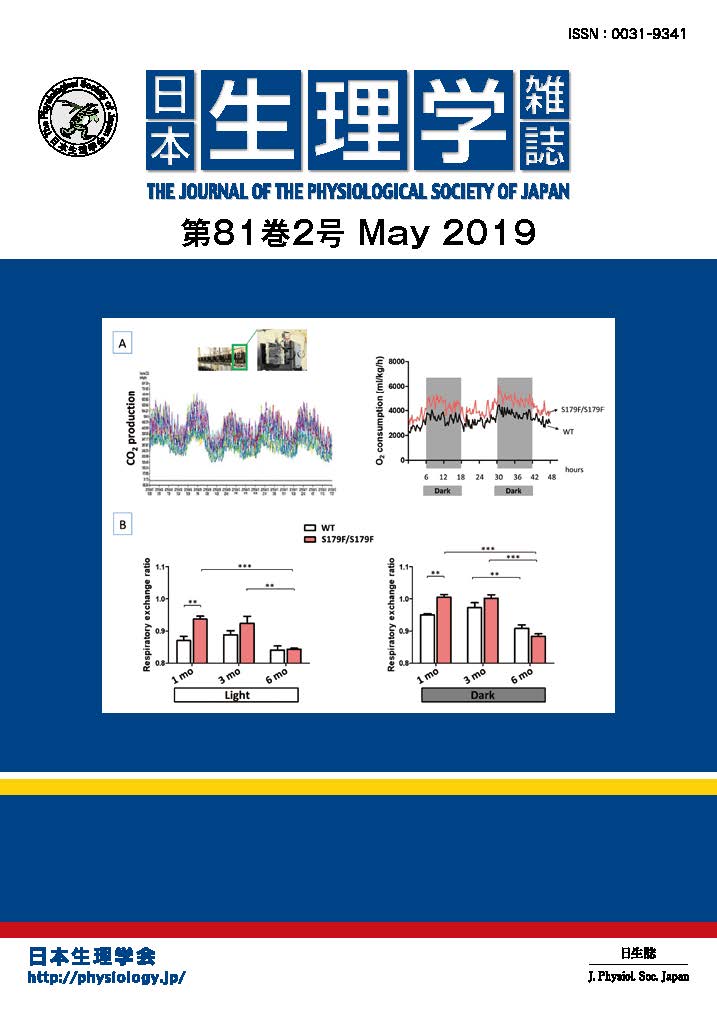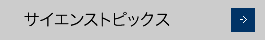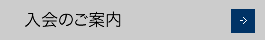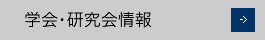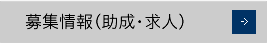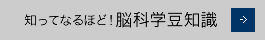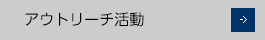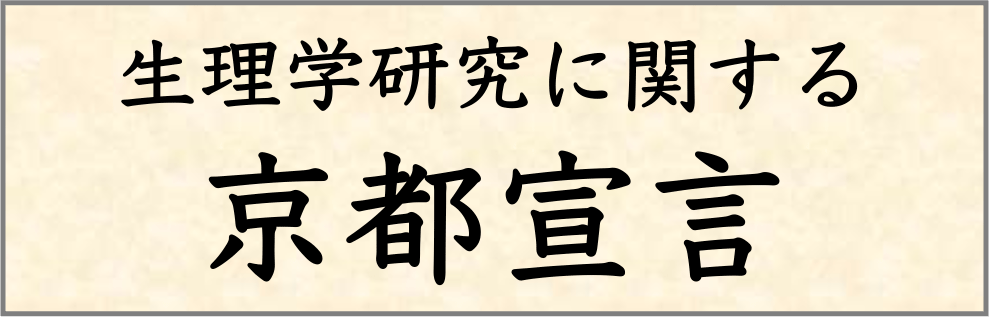東京女子医科大学医学部第二生理 宮崎俊一
西暦2000年を迎えた。この切りのいい年に巡り合わせたことは、1000年に一度ということを考えると、幸運とも思えてくる。またふと歴史をふり返り、未来を想う気持ちにさせる。今から1000年前の時代というと、年表では十字軍開始より約100年前、神聖ローマ帝国、宋、平安朝藤原道長が勢力を強めていくころとある。遙か昔々の世界である。1000年後の未来は、超加速的な近年の変化を目のあたりにして、遙かに想像を超える。せめて100年、いやそれすらが難しい。20世紀の科学は、前半は物理学、後半は生物学の時代と言われ、キーワードは原子核とDNAとされる。生命科学の時代は、科学技術の進歩と高度情報化と相まって、このまま当分継続しそうである。他方、資源や環境といった現実的問題への科学のさらなる関与の必要性が予測される。
このような時点で生理学会員として想うことの一つは、本誌巻頭言に既に論じ尽くされた感はあるが、「生理学の行方」であろう。「生理学」を標榜しているものに、講義科目・教科書・講座・学会などがある。大学院大学制を導入した大学では生理学講座は既に消失しており、私共の大学のように学部教育に統合カリキュラムを採用した場合は生理学という講義科目はない。研究室での研究内容・実験手法も従来の生理学とは大きく変わってきており、スタッフの出身学部も多様である。学会あるいは研究成果を見ても、対象が生体・器官系から細胞レベルになるにしたがって、生理学というアイデンティティーが見失われそうな状況にある。上記のような教育システムを経た卒業者が増えてくると、生理学(少なくとも語としての「生理学」)という意識は益々希薄になると予想される。そこで従来の生理学教室で育ってきた我々の生理学者像を改めて考えてみるに、生体・器官・細胞のダイナミズム(発達や病的変化も含めて)に興味を持ち、どのようにして動くのかを見るために、生きた系で可能な限り定量性を持った実験系を開発して記録・解析し(多くの場合記録の横軸は時間)、解析しつつも究極的には種々の生物・生体現象の総合的なメカニズムを解明したいという希求を秘めたロマンチストというところか。してみると「ダイナニズムは?メカニズムは?」という問いが頭から離れない「機能へのこだわり」の強さが生理学のアイデンティティーではないかという考えにたどりつく。 生物あるいは生体機能の解明にはもちろん形態や物質の知見が必須であり、現在最も先鋭的に展開されている分子生物学は極めて有用である。それらの研究もしかし、いずれそのベクトルは機能へと向かい、機能解明への高次化が、次の必然的な発達段階であるに違いない。ポストゲノムはそのベクトルを指すのであろう。このような観点から、機能学の立場は必然的に存在し続けるはずである。「生理学」という名称に必ずしもこだわらずに、何々機能学という教科書が出てきてもいいと思うが、ノーベル賞の領域に(医学・)生理学としているおそらく生きる理に迫る生物学という希求を込めた広義の「生理学」という語は、座右の銘的に生き続ける必要がありそうである。我々生理学会員は、機能へのこだわりというアイデンティティーをより鮮明にしていく必要があるように思える。学会の進展は、医学部生理学教室の枠をさらに越えて、機能にこだわる同志を引きつけることにかかっているのではないだろうか。てこ入れとともに、名称を国際学会のように生理科学会とするのはどうだろうか。 科学の進展は、天才的な研究者の突出した偉業と、そのギャップを埋め先端を広めていく多数の作業の繰り返しからなることが歴史から読みとれる。進展の幅は大小様々であり、個々の研究者は夫々に役割を果たしている。業績の真の評価は歴史の歳月に耐えたのち、画期的(epoch making)と評される。昨今の我々は眼前の評価に曝され、研究費の審査、役職の選考といった現実的問題を意識させられる。なんとなく住み心地のよくない時代はさらに進むものと思われる。その評価には通常重要である(important)あるいは意義がある(significant)という基準が用いられる。研究費申請時には(忸怩たるものを感じつつも)自らの研究をそう評している。しかし研究には別の側面があり、別の評価もある。日常の研究活動を実際に駆動しているのは、未知なるところを知りたいという素朴な欲求と、面白いという主観である。そして自分たちの仕事を他の研究者に話したときに、“Interesting!”という言葉が嬉しい評価である。シンポジウム講演後に、座長の美辞よりも“I enjoyed your talk.”という一研究者の語りかけによって報われる。私がかつて留学した萩原長生先生(昨年10回忌の記念シンポジウムがUCLAで開かれた)は、Interestingの他に、記録が美しい(beautiful)、データがごたごたしたdiscussionを要しない程に鮮やか(bright)あるいは優雅(elegant)であることを要件として挙げられ、実践しておられた。また研究者の生物学的センスを重視された。これは研究者が生命現象の面白さと機能解明への糸口を本能的に嗅ぎとっているかということに思える。 ともあれ、主観・客観の評価の中で研究の営みは継続され、時が流れ、数十年もすれば殆どの論文は土に埋もれ、あたりまえの知見として地盤を築いているであろう。