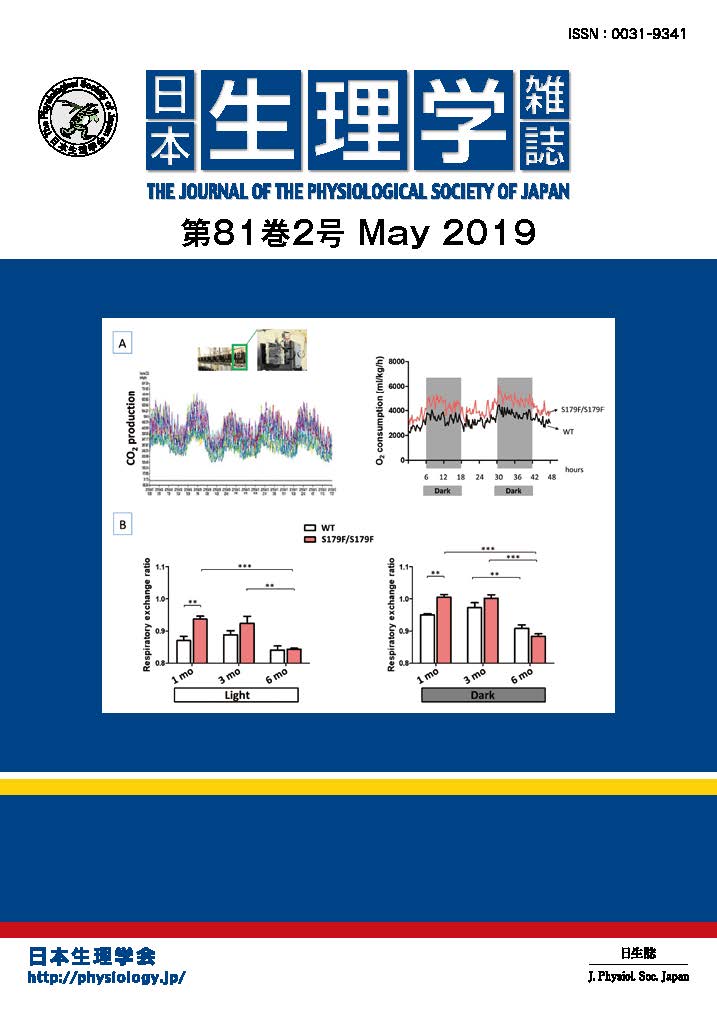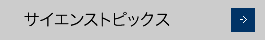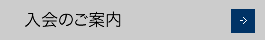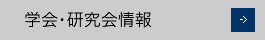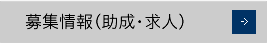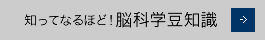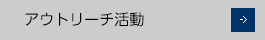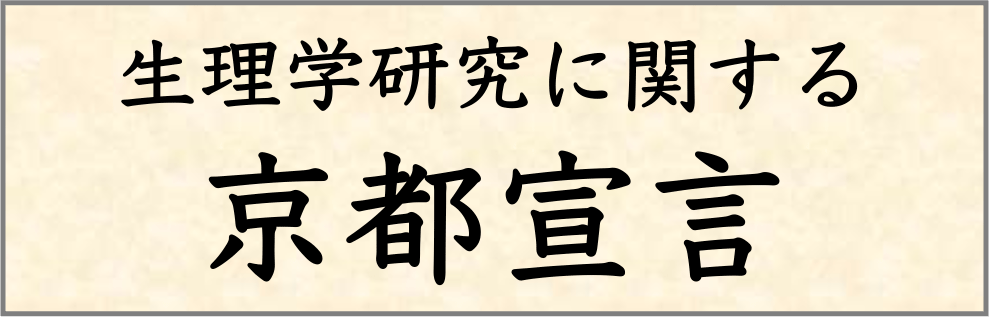東北大学医学部生体システム生理 丹治順
少しばかり趣向を変えて、「生理学者群像」という観点から話を進めてみようと思う。私にとって忘れられない「生理学者」の記憶痕跡として、二つご紹介し たい。イギリスの某大学生理学教室の、高名なM教授にお会いしたとき、まず驚かされたのは、頭脳の明晰さである。著書を読んで感じていた論理構成の完璧さ と美しさから、並外れた知力を想定してはいたものの、いざお会いしてみると、研究の深さと、会話のなかにほとばしり出る知性に、あらためて感動せざるを得 なかった。M教授の論文が一点非のうちどころが無い理由も自明であった。ところがいざ研究室を見せていただいたとき、その古風なことに驚きを禁じ得なかっ た。およそ現代風の利器といえる装備・器具が無く、古ぼけた脳脊髄固定装置と実験器具が並んでいるのみであった。これで充分研究ができるし、コンピュー ターなどは不要とおっしゃるM教授の説明には納得しても、研究者の狭く寒々とした光景はあまりにも寂しかった。最も気になったのは、若手研究者が見当たら ないことで、ここしばらく大学院生などはいないということであった。絞り込んだ研究テーマから離れようとせず、すでに確立された手法で、あくまでも完全を 期する研究者としての姿勢に頭が下がる思いではあったが、その挙げ句、研究の後を継ごうとする若者が絶えてしまった現実に限りない哀惜を感じながら、この うえもなく典雅なキャンパスをあとにした。
もう一つの記憶は、J. Neurophysiologyの編集会議に際しての体験である。最近Impact Factorが低落傾向にある。この傾向に歯止めをかける方法は無いものか。Impact Factorなるものは、単なる1企業が2年間という極めて安易な調査で論文の引用の尺度として公表しているもので、へんぱな情報でしかない。しかしそれ がここまで広まってしまい、利用(悪用)されてしまうと、放置できないではないか。それならばImpact Factorが上がる人工的方策を考えて、逆用を計るのも悪くはなかろう。そのための具体策はいくつもあろう。そんな議論が行われていた。しかし複数のメ ンバーから異論が出された。特にG教授のコメントは強烈であった。Impact Factorが低くなろうと、それを問題にする方がおかしい。掲載論文自体の価値を見抜くこともできず、小児的な発想でImpact Factorの数字いじりによって問題を処理しようなどという者は学者ではない。そのような人種を相手にする必要などあろうか。そもそもJ. Neurophysiologyは長期的な展望のもとに系統的な研究を行い、その成果をもとに新たな学説を提唱するような論文を扱うので、論文の Turnover Cycleは長いのが当然であり、その評価が確立するのに数年を要するのが通例である。つまりImpact Factorなどは超越した価値を持つ論文を掲載することがこの雑誌の使命である。その発言の迫力で、人工的方策の話は沙汰やみとなった。
生理学とは何かという問の答えには、「…の機序を追求する」、「…のはたらきを考える」という表現が多いことからしても、生理学は“考える”学問 であり、知恵の学問といってよかろう。多くの先人達は生命現象を見つめ、多様な手法で生命の現場に立ち入り、“どうしてなのか”と問い続けてきた。そして 生理学者の多くは、考えることを確かに楽しんできた。しかしその反面、生理学者は一般に、自らの属するコミュニティや研究環境の改善・発展について、“知 恵”を働かせることに消極的であり過ぎたのではなかろうか。平たく言えば、研究ポジションの確保や研究費の拡充、もっと大事なことは若手研究者の参入促進 への努力を軽視する傾向は無かっただろうか。ある時、若者の多く集まるセミナーで「生理学者の印象を表現すると?」と問うてみたところ、「まじめ、慎重、 正統的、論理的」と言う反面、「保守的、批判的、懐疑的、消極的、暗い」というものや、「お高くとまっている」等という答えもあった。これから医学・生物 学の研究を志そうという若者達にとって、生理学者群像の与える印象がネガテイィブであったとすれば、是非ポジテイブに変えたいものである。
これは言い尽くされた感があるが、生理学研究の手段と可能性が今ほど急拡大した時代は無かろう。テクノロジーの進展とコンピューターの利用の普及 に加え、分子生物学の発展は、いままで夢にも思わなかった(あるいは今までは夢に過ぎなかった)研究を一挙に可能にしてしまった。筆者の属する大脳の高次 機能を知ろうとする研究分野についても、技術革新とコンピューター導入の次には分子生物学的技術の利用が盛んに行われている気運が見えている。たとえば局 所的・要素的機能脱落法として、リセプターアゴニスト・アンダゴニストの利用は重宝であるが、やがて遺伝子工学的技術の導入も本格化しそうである。 Antisense ablationや遺伝子組み替えウイルスによる特異的機能脱失法、あるいはノックアウト動物の応用等も、現状では中枢性機能研究については問題が多いと はいえ、まもなく問題点を克服する技術と知恵が生まれよう。大切なことは、生理学者はそのような挑戦的な研究の欠陥をあげつらい、論理的に稚拙であるなど といって冷ややかに傍観するのではなく、むしろ共同研究者として積極的に参加し、使い物になる技術に仕上げることに貢献することではなかろうか。
生理学者の特技は機能を考えることにある。「単にどこに何があるかという、物質の同定だけを目指す、いわゆる“物取り”的研究には、生理学者は満 足しない。そのような研究は、ゲームにたとえれば、詰め将棋の世界である。生理学者はむしろ全局を見通しながら、一手ずつを進め、その意味を考えようとす る。そのような生理学者こそ、最近ますます急進展する分子生物学的研究の知見を把握し、統合することによって、複雑な生命体の機能を理解する研究の新たな 方向を先導する適役者ではなかろうか。新しい道具と戦略がこれほどまでにそろってきたいま、それらを使って意味のある作戦に仕上げる知将がが必要である。 それが、これからの生理学者の分担すべき役割ではなかろうか。次世代の生理学者には、広い研究分野の理解のうえに多領域が参加する共同研究の主役を勤めな がら、考えることを楽しむように望みたいものである。その実現のためになすべきこたがいかに多くはあっても。