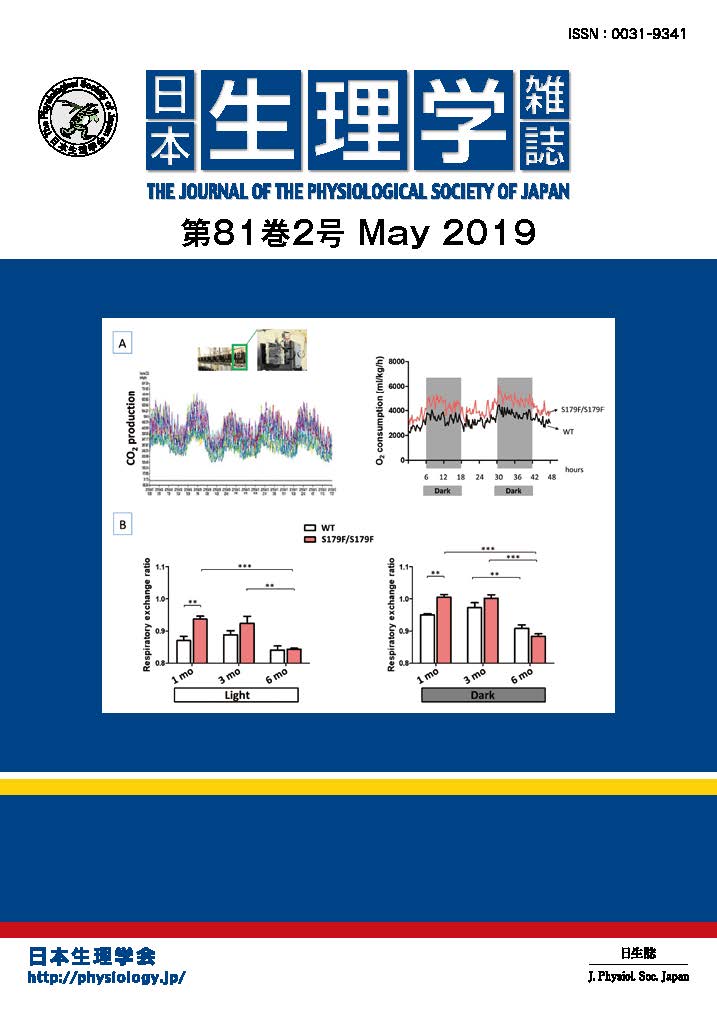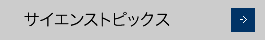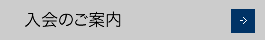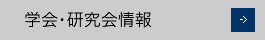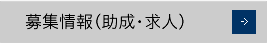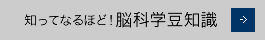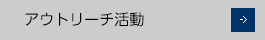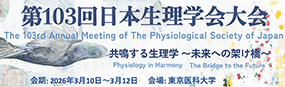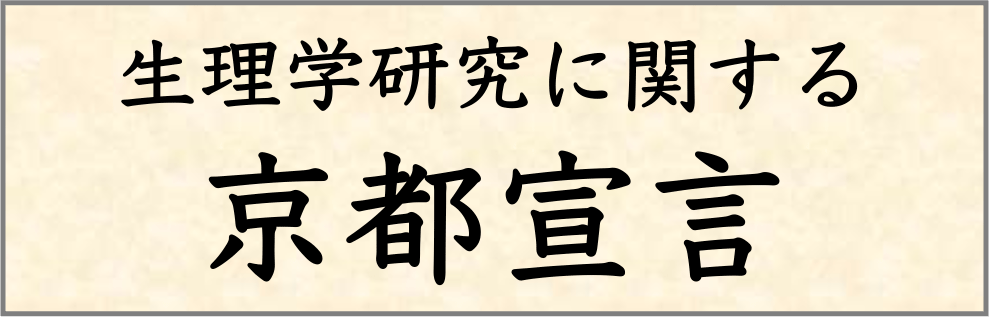大阪大学医学部 福田 淳
行く河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは 、かつ消え、かつ結ぴて、久しくとどまりたる例なし。鴨長明の方丈記のはじめであ る。戦乱に明け暮れた時代を生きた一世捨人の達観に驚かされる。この洞察は20世紀 の量子力学の隆盛を待つまでもなく、物事の二面性をいみじくも言いあてている。河 の流れは波動であり、かつ粒子の動きであると。我々の生そのものも、この二面性を 持っている。現象としての生理と分子の集まりとしての面と。生理学は分子生物学に 席捲されているという。果たしてそうか。筆者はそうは思わない。よく学生に生理学 の講義をするときに、分子生物学は例えば文章の中の「あ」なら「あ」の構造を詳し く調べ、それが「ア」であったり「A」であったり、「a」であったり、いくつかの亜 型にわかれることを調べているに過ぎないのであって、我々が本当に文字を理解しよ うとすれば、「あ」はどういう文字とつながり、どういう言葉が生じ、意味ある言葉 がどうつながって文章になり、また文章がどう配列されて感動させる文になるか、そ のそれぞれの次元での文法を明らかにしていかなければ、本当に高度なものの成り立 ちは理解できないと説く。デカルト以来、困難なものは分解して要素に分ければ理解 しやすいという。しかし、例えば脳の働きを理解するのに、学習・記憶→ニューロン 活動の時間的変化→シナブス可塑性→伝達物質放出変化・受容体活性の変化→蛋白質 のリン酸化→遺伝子発現調節というように還元してゆくと、これら一連の連鎖はすべ て必要条件をたどっているに過ぎず、逆向きに十分条件を検討していないことになる 。その自覚から最近、一足飛ぴに遺伝子とその機能分子の発現を障害して統合された あとのグローバルな機能(行動)の異常を調べる、いわゆるノックアウトマウスで機 能障害を調べる研究が盛んである。我々も京大・中西研と共同で、網膜のmGluR6ノッ クアウトマウスでON反応が消えることを生理学的に証明することができた。しかし、 これだけでは実につまらない。我々電気屋は、分子屋がON反応の受容体を壊したのを まるで配線が切れたことをテスター代わりに証明したに過ぎない。生理学的に面白い のは、むしろ遺伝子レベルである因子がないにもかかわらず、その動物はいかに外界 に適応して生存してきたかというところにある。我々生理学者にとっての関心事は、 生体が単なる部品の寄せ集めでなく、一つの寿命を全うすべく、内的・外的障害因子 にかかわらず、生存する術をどのように身に付けているかを知ることである。生命体 のもつ不思議さ、生きることの素晴らしさ、そういうものをよりよく知るところにあ る。我々が“神経の再生”の問題に取り組んでいるのも、こういう観点からである。 生き続けることに坑するさまざまの障害因子にもかかわらず、機能を修復して生命体 の本質でもある生き続けることを可能にする生体のメカニズムを知ることは、生理学 の一つの課題であるとも考えられる。一方で、医学における生理学は単に生命現象を 理解してよしとせず、やはり人間の身体を治すという目的性を持つ必要がある。“神 経再生”の問題は、21世紀の高齢化社会での脳障害の治療法の開発にもつながる研究 課題でもある。いかに分子生物学・分子遺伝学が隆盛であろうと、我々はこれらの技 法を駆使し、もっと大きな人間のよりよき生存の理法の解明とその応用に立ち向かう べきである。生理学会はどうあるべきか、それは簡単である。一つの集団が存続し発 展するためには新しい会員を増やすこと、民主的運営を行うこと、世代交代を有効に はかることである。それには分子生物学を専攻したものも合めた若い生理学徒の力を 充分に引き出すことが肝要で、そのためには学会に学生会員制をつくり経済的負担を 軽減すること、若手奨励賞を設けて若手の研究をencourageすること、若手中心のシ ンポジウムを開くことなど、早急に手を打つべきである。