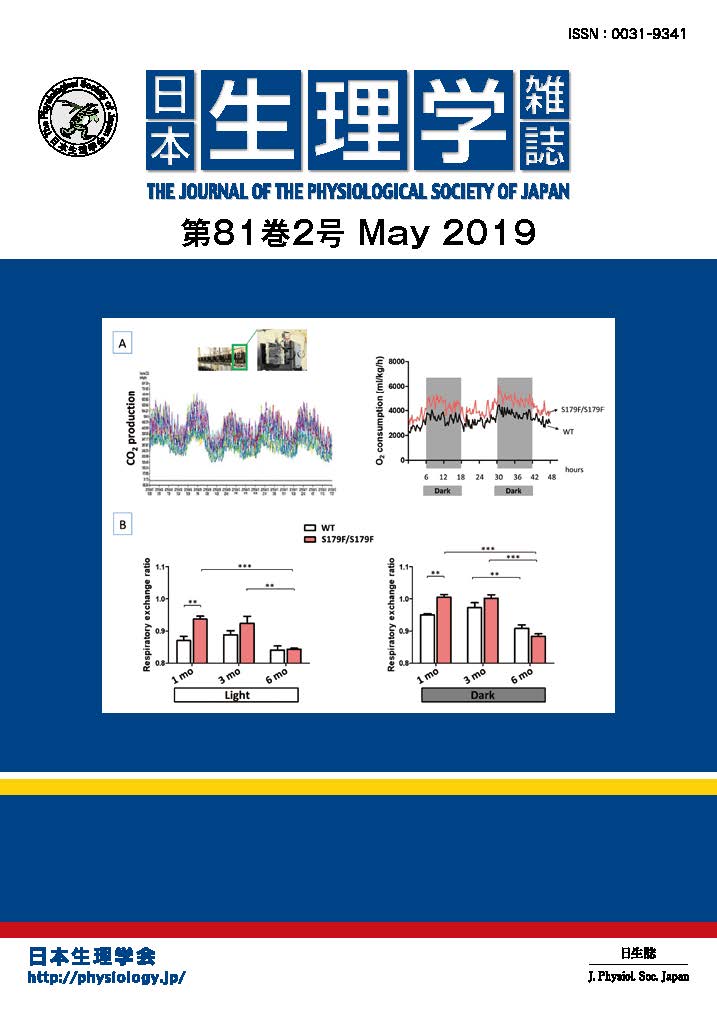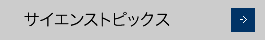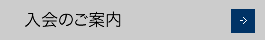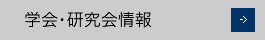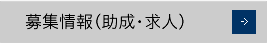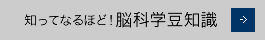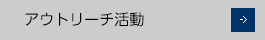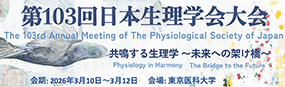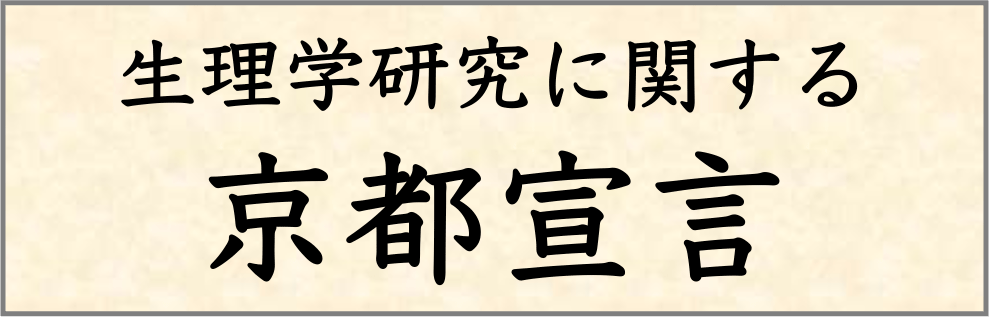大阪大学医学部バイオメディカル教育研究センター 高次神経医学部門 津本忠治
20世紀も終わりに近づき、生命科学研究は最近益々進展の速度を速めているように 見える。新しい技術や装置の導入、学術集会の相次ぐ開催、原著論文の爆発的増加な ど、どれをとってみても生命科学の進歩の激しさは明らかである。この加速度的な生 命科学研究発展の牽引車として中心的役割を果しているのは、現時点では、分子生物 学といえるであろう。例えば、私が専門とする神経科学領域でも、シナブス受容体の クローニングによる一次構造の解明とサプタイプの確立、体節構造や神経回路の発生 を制御する遣伝子群の同定等、目ざましい成果をあげてきたのは分子生物学であった 。特に、最近、目標の遣伝子をノックアウトした動物作成法の開発により、特定の機 能分子と個体行動を直接的に関係づけることができるだろうとの期待のもとに多くの 研究がなされつつある。
このような動向を背景にして、最近、多数の分子生物学者が細胞生理学や神経生理 学の領域へ進出しつつあるように思える。現に、一部の大学ではあるが、分子生物学 者が従来の生理学教室を主宰する場合もみられるようになった。特に憂慮すべきこと は若手研究者が分子生物学を指向し、その方法論でもって研究を行ってこと足れりと する傾向が強いことである。このような時流の中で生理学者は何処にアイデンティテ ィーを求めるべきなのであろうか?生理学に若者を引きつけるような未来はあるのだ ろうか?
ここで私は、It is physio1ogy that breathes life into anatomyという古い言葉 を引用しそこに込められている思想を強調したい。ただし、上述した理由で現在はan atomyをmolecular bio1ogyに変えるべきかも知れないが。確かに、分子生物学は受容 体やセカンドメッセンジャー等、生体を構成する機能分子の一次構造は明らかに出来 るかも知れない。確かに、ある物質の関連遣伝子を欠如した動物は作れるかも知れな い。確かに、特異的神経結合を作り上げる蛋自質は明らかに出来るかも知れない。し かし、それらの受容体やメッセンジャーがどのように組み合わさって生きた細胞が機 能するのか、さらにはそれら多数の細胞がどのように統合され、生体としてあるいは システムとして働くのか、は生理学なしにはわからないのである。生きた細胞や生体 をオンラインで時々刻々“生きたまま”観察・分析するという思想に裏打ちされた生 理学なしにはそのような機能は結局はわからないであろう。まさに、分子生物学的、 生化学的あるいは形態学的知見に命を吹き込み生命科学として意味あるものにするの は生理学である。 しかし、そのためには生理学は従来の方法論に安住することは許 されないと思われる。分子生物学を始めとする最近の生命科学の新しい展開に対応で きるように自己を革新する必要があろう。単に分子生物学だけでは生命はわからない と唱和し、生理学は時間がかかり、それ故結果の発表が少ないと言い訳的言辞を奔す ることはつつしみたい。従来の生理学の観察、計測、解析法を越える新しい技法の開 発と今迄にはなかった新しい概念の創出が必要であろう。それなしには、関連研究分 野を凌駕し、若い研究者を生理学に引きつけることはできないであろう。その意味で 、我々生理学者の時代を先取りした意識改革が望まれている。